海に関する本の紹介
私の所有する『海本』の紹介をします。コメントは、私の主観によるものですので、御了承下さい。
ジャンル別索引
ジャンルをクリックで、ジャンプ!
図鑑 写真集 スキル・安全 南の島 読み物 漫画 カメラ
書名別索引
書名をクリックで、ジャンプ!
図 鑑
25冊
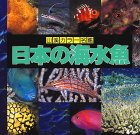 |
日本の海水魚 | |||
|
岡村収・尼岡邦夫 編・監修 山と溪谷社 \5400+tax 1997年8月20日 初版1刷発行 1998年12月18日 購入 |
||||
|
日本産海水魚が、約2400種も載っており、目・科名、大きさ、分布域、生息場所などのデータのほか、
形態(同定に必要な最低限の判別点)、生活・習性・食性、利用(料理法や食味)、別名も解説してあり、
たいへん便利である。さらにお馴染み?の水中カメラマンが撮った生態写真が中心で、
雌雄、色彩変異、老若、幼魚についても、掲載されており、ログ付けがしやすい。 どこのショップのログ付けでもたいてい出てくる定番の図鑑であるが、 定価が\5400と高価なので、なかなか個人のダイバーで持っている方は少ないのでは? |
||||
 |
 |
決定版 日本のハゼ | ||
|
瀬能宏 監修 鈴木寿之・渋川浩一・矢野維幾 著 平凡社 \3800+tax 2004年9月24日 初版第1刷発行 2004年10月21日 購入 |
||||
|
「日本のハゼ亜目335種と、国内未記録種・未記載種135種をすべて水中の自然状態で撮影。
ポイントをおさえた解説で、近似種との違いも一目瞭然。」(オビ紹介より) ハゼ好きには、たまらない一冊である。写真もきれいで、見ていて楽しくなるし、 「今度は、このハゼ見たいな。」とワクワクしてくる。見たことあるハゼでも、 自分の撮影したものより綺麗な写真(ほとんどですが・・・。)が載っていると、 「こんな風に撮りたいなぁ!」と思わせられる。 「この本に載っていないハゼはない。」と言っても過言ではないと思う。 定価が\3800とちょっと高価であるが、内容からみて、コストパフォーマンスの高いものだといえる。 |
||||
 |
ハゼガイドブック | |||
|
林公義・白鳥岳朋 著 TBSブリタニカ \2800+tax 2003年3月6日 初版発行 2003年3月12日 購入 |
||||
|
「日本初、本格的なハゼの生態写真図鑑。約70属280種を掲載。約400点の写真と詳しい解説で、
種の特徴、見分け方、分布、名前の由来などを説明。」(オビ紹介より) この本が出たときは、衝撃的であった。ハゼだけの図鑑である。ハゼ好きには、たまらない一冊である。 写真もきれいで、見やすく、ダイビングで見たハゼのログ付け・・・、 撮影したハゼの同定に凄く役立っている。 また、コラムも面白い。コラム「この人、このハゼ」では、ナカモトイロワケハゼ、 ヤノダテハゼ、カサイダルマハゼなどの有名なダイビングサービスのガイドさんの名前を 冠したハゼを例にしながら、学名、和名などについて語られている。 「ハゼの撮影」では、接近方法、図鑑用写真など撮影の極意が掲載されている。 自分は、図鑑のようなカチッとした写真も好きであるが、 ボケ味を利かせた柔らかくて明るい写真も大好きである。 自分の撮影スタイルと比較して見ると面白いのでは? |
||||
 |
海の甲殻類 | |||
|
武田正倫・奥野淳兒 監修 峯水亮 著 ・・・著者サイン入り 文一総合出版 \3800+tax 2000年11月1日 初版1刷発行 2000年11月4日 購入 |
||||
|
水中カメラ、特にマクロを始めて、たくさんの小さなエビやカニ達を見つけて、喜んで撮影していた頃、
そのモデルであるエビカニの名前が分からず、なにかいい図鑑はないかと思っていた。
そんな時、発売を知り、即購入。 見たことのない、甲殻類がたくさん載っている。エビカニはもちろん、 ヤドカリやシャコの仲間もたくさん載っている。生態なども比較的詳しく、 近似種との見分け方なども分かりやすく書いてある。 エビカニ好きの定番の一冊である。 |
||||
 |
エビ・カニガイドブック 伊豆諸島・八丈島の海から | |||
|
加藤昌一・奥野淳兒 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2001年6月27日 初版第2刷発行 2001年7月14日 購入 |
||||
|
種の解説にあたって、分類学的特徴、問題点、分布などを奥野氏が・・・、
八丈島における生息状況や生態などのダイバー支店の観察記録を加藤氏
(八丈島でダイビングショップ経営)が担当している。
すごく分かりやすい。写真もきれいであり、見ているだけでも楽しい。 また、コラムでは、「シャコ・パンチの破壊力」や「カラッパの缶きり」など、 たいへん面白く興味深い話も読むことができる。 |
||||
 |
エビ・カニガイドブック2 沖縄・久米島の海から | |||
|
川本剛志・奥野淳兒 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2003年7月17日 初版発行 2003年7月18日 購入 |
||||
|
広い海中でひっそりと暮らすエビやカニ。だがその生き様は、こんなにも楽しげだ。(オビ紹介より) この本も、写真がきれいである。図鑑らしくない正面顔の写真(エンマカクレエビ等)なんかもある。 コラムも面白い。 |
||||
 |
 |
沖縄のウミウシ −沖縄本島から八重山諸島まで− | ||
|
小野篤司 著 ・・・著者サイン入り ラトルズ \2838+tax 2004年7月1日 初版第1刷発行 2007年1月1日 購入 |
||||
| ず〜っと、購入しようかどうか悩んでいた本書をついに購入した。 購入に至らなかったのは、既に、3冊のウミウシガイドブックを持っていたからだ。 ただ、その中の小野にぃ〜にぃ〜のウミウシガイドブックは、初版だったために、色々不満もあった。 (詳細は、ウミウシガイドブックの項を参照ください。) だからといって、似た様な本書を購入するのは、凄くためらわれた。 また、最近、「ウミウシ図鑑.com」というweb上の図鑑が結構便利で、 名前のわからないウミウシのデータベースとして、よく使うようになっていたので、 更に必要性はなくなっていた。しかし、ヤフオクで、「送料込み2割引」 (←これって、もしかしていけないこと?・・・今、気付いた。)かつ 著者サイン入りの本書があったので、思わず購入してしまった。 やっぱり、購入して良かった。眺めているだけで、なんだか嬉しくなってくる。 今度は、どんなウミウシに会えるのだろう? | ||||
 |
ウミウシガイドブック 沖縄・慶良間諸島の海から | |||
|
小野篤司 著 TBSブリタニカ \2400+tax 1999年7月2日 初版発行 1999年7月2日 購入 |
||||
| たぶん、初めてのウミウシ図鑑と言っていいのではないか? この本が出るまでは、ウミウシの名前を調べるのは、記憶を頼りに過去の雑誌をめくるか、 インターネットで調べるかであった。 自分は、小野にぃ〜にぃ〜のHPを、よく利用させていただいた。 その小野にぃ〜にぃ〜のウミウシ図鑑が出るということで、 即買いしてしまった。ちょっと残念なのは、初版に対し、第2版以降、大幅に名称が変わったことである。 飛び付いて買った初版では、標準和名のないものは、学名のラテン語がカタカナ表記されていた。 大好きなミゾレウミウシもゾウゲイロウミウシも、それぞれクロモドーリス・ウィラニ、ブロッキィとなっていた。 そう、第2版以降は、わかりにくい学名のカタカナ表記ではなく、仮称(通称など)が多用されているのである。 だれか、第2版以降のものと換えてくれませんか? | ||||
 |
ウミウシガイドブック2 伊豆半島の海から | |||
|
鈴木敬宇 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2000年4月2日 初版発行 2000年?月?日 購入 |
||||
| 続編ということで、なんと伊豆の海編である。伊豆の海のほうが、 沖縄よりも身近と言うことで、知ってるウミウシも多いかと思いきや、 1よりも見たことあるウミウシが少ないのは何故だろう。 自分は、ウミウシ探すのが、すごく下手なんだと思い始めた頃に購入した本である。 だから、あまり見ていない。デジカメで、もっと気軽にウミウシ撮影すれば、 ウミウシ探しの目が養われるかも・・・。 そうだ、京都のFさんや、三重のOさんのように・・・。 彼女達は、ウミウシ探し&撮影の先生である。 | ||||
 |
ウミウシガイドブック3 バリとインドネシアの海から | |||
|
殿塚孝昌 著 阪急コミュニケーションズ \2400+tax 2003年8月20日 初版発行 2003年9月11日 購入 |
||||
|
ポップ、キュート、アバンギャルド。「海の宝石」たちは奇想天外!(オビ紹介より) 第3段ということで、思わず、買ってしまいました。 1も2も、あまり利用していなかったというのに・・・。 でも、中身はみてびっくり。すごくきれいなウミウシが多いのである。 あぁ〜、バリやインドネシアの海に潜ってみたいよぉ〜! |
||||
 |
 |
ナマコガイドブック | ||
|
本川達雄・今岡亨・楚山いさむ 著 阪急コミュニケーションズ \2200+tax 2003年8月20日 初版発行 2003年9月11日 購入 |
||||
|
のんびり生きる究極の省エネ生物には現代人が学ぶべき叡智が隠されている。(オビ紹介より) 日本近海で目にする約50種のナマコが載っている。でも、ただの図鑑ではない。むちゃくちゃ、面白いのである。 まず、Q&Aとして、「どこに住んでいるか?」とか、「なぜナマコというのか?」とか、 「中華料理屋に出てくるのは何ナマコか?」とかの34問で、ぐいぐい引き込まれる。 (某TV番組のへぇ〜って感じ。・・・知っていたからって、なんの役にも立たない。たぶん。) そのまま、ナマコの特徴、ナマコ学の基礎講座とどんどん引き込まれていく。 最後は、海で見かけるあのナマコたちの図鑑(135ページ中、たった20ページぐらい)で、締めくくられている。 とにかく、学問的なことを生徒と先生の会話形式で、ユーモアも交えながら、教えてくれる。 ナマコは、棘皮動物で、ウニ、ヒトデ、クモヒトデ、ウミユリの仲間。 そして、「棘皮動物っていうのは、みんな、5が、基本だぁ〜。」そんな内容が、楽しく載っている。 この本のおかげで、ナマコのことを好きになってしまった。 |
||||
 |
クマノミガイドブック | |||
|
ジャック・T・モイヤー 著 余吾豊 訳 TBSブリタニカ \2200+tax 2001年7月9日 初版発行 2001年7月11日 購入 |
||||
|
クマノミっていうと、ガイドさんに「日本には、6種類いるんだよ。」と教えてもらいませんでしたか?
そして、「1ハマ、2クマ、3カクレ」などの見分け方を教わった方も多いのでは?
それだけ、ダイビングでは、目立って可愛い存在である。意外とシャイで、臆病なカクレクマノミ。
結構攻撃的なトウアカやクマノミ。グローブをかまれた人も多いのでは? 自分は、白化したイソギンチャクをバックにちょっと露出オーバー気味にして、 おもいっきりぼかして、オレンジ鮮やかなクマノミやハマクマノミの幼魚を撮りたい。 ちょっと閉じかけたセンジュイソギンチャクに潜り込んでこちらを伺うカクレクマノミを バックを青抜きで、撮りたい。このダイバーに身近なクマノミ達の世界のお仲間を紹介した図鑑なのである。 |
||||
 |
チョウチョウウオガイドブック | |||
|
中村庸夫 著 阪急コミュニケーションズ \2400+tax 2003年4月22日 初版発行 2003年7月18日 購入 |
||||
|
美しく愛らしい全世界の蝶々魚を一挙掲載。海洋写真家中村庸夫が世界の海で撮影した決定版!
チョウチョウウオ科119種を収録。(オビ紹介より) 初めて、南の島の海を潜った時に眼に入ってきたのが、チョウチョウウオであった。 今では、見向きもしなくなったフエヤッコダイ。黄色くて、いかにも熱帯魚らしくて、見つけるとワクワクしていたのに・・・。 個人的に好きなのは、ミスジチョウチョウウオ。こいつらは、珊瑚礁の元気度を計るバロメーターなんて話を 聞いたことがある。(この本ではないけど・・・。)写真に撮りたいのは、定番だけどトゲチョウチョウウオ。 浅めの白い砂地に1本のエダサンゴを手前に配して、2匹が寄り添うように砂地の上を悠々と遊泳。 もちろんバックは、明るく青抜き。・・・あと、見たいのは、ユウゼンである。 とにかく、この本は、たくさんのチョウチョウウオが載っている。 生息地域がそれぞれ世界地図に記入されているのは、たいへん判りやすい。 見ていて、きれいではあるが、今は、ハゼ、エビカニ系に心を奪われているので、 名前を覚える気には、なかなかなれませんねぇ。 そうそう、サイパンでのカスミチョウチョウウオ。あんなに群れて、ダイバーに迫ってくるのには、びっくり。 ちょっと、引いてしまった。餌付けしていたのかなぁ。。。ちょっと、気持ち悪かった。 |
||||
 |
幼魚ガイドブック | |||
|
瀬能宏・吉野雄輔 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2002年9月30日 初版発行 2002年10月12日 購入 |
||||
|
親子がこんなに違うなんて!不思議な海の魚たちの写真図鑑。(オビ紹介より) かわいい幼魚と言えば、私が思いつくのは、黄色に黒の水玉模様のミナミハコフグ、 オレンジ色に白い斑点?のツユベラ、背ビレの眼状斑が目立つカンムリベラ、 白と赤オレンジの体をいつも曲げたままで泳いでいるイロブダイ、ウズマキ模様のタテジマキンチャクダイ、 近づいて驚かすと砂に潜ってしまうホシテンスなどなど。そんな幼魚たちと親の写真を比較しながら楽しめる。 浅場の珊瑚の根でデバスズメダイなどに混じって泳いでいた白くて黄色くて青いヒレを持つ魚が、 クロスズメダイの幼魚と判ったときには、ちょっと感動した。 |
||||
 |
ヒトデガイドブック | |||
|
佐波征機・入村精一・楚山勇 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2002年7月5日 初版発行 2003年7月18日 購入 |
||||
|
世界初、海の星カラー写真図鑑。日本沿岸産のヒトデ&クモヒトデを約150種(新称25種)掲載。
生態写真を中心に特徴、見分け方、生態、分布など詳しく解説。
ユニークな生態、不思議な現象などの興味深いコラムを満載。(オビ紹介より) ヒトデは、ダイビングで見ても「ヒトデいたねぇ〜」と言ってもらえれば、ましなほうで、 ほとんどの方が無視しているのではないか。ヒトデはひとまとめに「ヒトデ」で、 ちゃんとした名前を知っている方は少ないと思う。 ただし、オニヒトデだけは、別格で、皆さんご存知だと思う。トゲトゲで、腕がたくさんあって、大きくて、 紫っぽいグレーの気持ち悪いヒトデである。珊瑚を食べる悪者のヒトデである。 他には、エビカニ好きな人は、よくエビがついているマンジュウヒトデは、 知っているであろう。個人的に、まだ見たことないが、テヅルモヅルは興味がある。 この図鑑を持っているだけで、ダイビングでヒトデに目をやることが増えると思う。 「これ、見た見た!」とか、「へぇ〜」とか、「ふ〜ん」とか言いながら、眺めることがある。 ・・・その頻度は、年に1回ぐらい!? |
||||
 |
イカ・タコガイドブック | |||
|
土屋光太郎・山本典暎・阿部秀樹 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2002年4月27日 初版発行 2002年6月28日 購入 |
||||
|
日本初、イカ&タコの生態写真図鑑。不思議でユーモラス!
イカ・タコ類をフィールド写真とビジュアルコラムで徹底紹介。(オビ紹介より) ヒトデガイドブックは、「世界初」だったが、こちらは、「日本初」。世界には、既にあるらしい。 結構身近な存在なのに、イカはイカ、タコはタコで済ましてしまうことが多いイカタコ。 (イカの方がちょっとだけ多くの種類を知っているかも・・・。アオリ、ヤリ、ホタルなど?) ・・・こんなにたくさんの種類がいるとは、驚かされた。 しかし、この図鑑を見ても違いが判るようになるのは難しい。生息場所、生態の違いで、 なんとなく判るようにはなる、きっと。 コラムは、面白い。イカのスミは、粘液性で、水の中でも固まっていて自分のダミーを作り出す。 タコのスミは、サラサラで、水の中では煙幕のようにタコを一瞬隠す。 「ダミー」と「煙幕」、中層を泳ぐイカと、 隠れる場所に事欠かないタコとのスミの利用法の違いらしい。 イカスミの粘液成分に制ガン、抗菌といった機能成分が含まれているらしい。「イカスミと違って からまりにくいぶん、タコスミは料理に不向きだとか」ということだが、もっと違う理由があるかも知れない。 タコスミ料理を聞かない件は、、前から疑問だったのだが、この本で解決はしなかった。 誰か知っている人がいたら、教えて欲しい。 |
||||
 |
イソギンチャクガイドブック | |||
|
内田紘臣・楚山勇 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2001年7月3日 初版発行 2001年8月25日 購入 |
||||
|
日本産イソギンチャク類のほぼすべてを掲載。貴重な生態写真を中心に分布、特長、見分け方など詳しく解説。
「食用になるイソギンチャク」「共生」「採集と飼育方法」などのコラムを満載。(オビ紹介より) イソギンチャクと言えば、仮面ライダーの 怪人「イソギンチャック」を思い出す。 と言っても、姿かたちを覚えているわけではなく、語感というか響きが耳について離れなかった。 当時、自分がイソギンチャクという生物を知っていたかどうかは、定かではないが、 いつの頃(小学校高学年?)からか、怪人の名前にしては、実在の生物に小さな「ッ」を 追加しただけのひねりのないネーミングに感動すら覚えていたものである。 初めて、大瀬崎で見たムラサキハナギンチャクは、幻想的であった。結構、好きなのが、 キンチャクガニのハサミに常に挟まれているカニハサミイソギンチャク。小っさくて、かわいい。 チアリーダーのボンボンのように振られているが、白ではなく、黄色(片方だけ、もう一方は、白だった。) のものを見たことがある。残念ながら、この本でもそんな色彩変異のことまでは、書いてなかった。 この本で、それぞれのクマノミと共生関係のイソギンチャクを知ることができる。 他にも、エビカニなどを撮影するのに、共生先であるイソギンチャクを知ると有利になると思う。 きれいな砂地でスナイソギンチャクをバックにして、オドリカクレエビのホバリングしながら 踊っている姿を撮ってみたい。もちろん、バックは青抜きで・・・。 |
||||
 |
海辺の生きものガイドブック | |||
|
倉沢栄一 著 TBSブリタニカ \2400+tax 2002年6月29日 初版発行 2002年6月28日 購入 |
||||
|
週末・夏休みの海が3倍楽しくなる!ヒトデ、クラゲ、エビ、カニ、貝類など
「身近な海」の生きもの総登場。沖や海底の生きものの写真・解説、
子どもの質問に答えられる「Q&A」も充実。(オビ紹介より) この本は、とにかく文字数が少ない。子ども向けのようでもあるが、そうでもないような気もする。 写真を多用と言うより、写真集に近いと思う。子どもが「海にはこんな生きものがいるんだ!」と 目をキラキラさせながら見ることができるような構成にしてある。 そんなにたくさんの種類が載っているわけではないが、 著者がどのような意図で選択したのか考えるのも面白いと思う。 例えば、エビカニのページでは、クルマエビやイセエビは、 なんとなく「身近」で「海辺」のという感じ(主観である。)はするが、 なぜイソギンチャクエビやフリソデエビが選ばれているのか? ・・・カニにいたっては、イシガニやシオマネキなどの身近な磯、干潟のカニは掲載されておらず、 「深海」に生息するタカアシガニ、ハナサキガニが選ばれているのはなぜか?と考えると面白い。 また、ウミガメの産卵やラッコやジュゴン、アザラシなどの哺乳類、さらに、要注意生きものや磯遊びの仕方まで 載っている。いろんな意味で、面白い。 |
||||
 |
伊豆・大瀬崎マリンウォッチングガイド | |||
|
奥谷喬司 監修 伊藤勝敏 著 データハウス \1350+tax 1999年1月5日 初版第1刷発行 1999年1月1日 購入 |
||||
|
この本は、たいへん役に立った。大瀬崎で見かけるほとんど全ての生きものが
掲載されていると言っても過言ではない・・・と思う。
この本を見ていると、大瀬崎というポイントがどれほど豊かですごい海であるかがわかる。
ダイビングで、タカアシガニが見られるなんて・・・、私は見たことはないが、
見られる可能性があるだけですごいことだと思う。また、携帯性も優れており、大瀬崎、いや、
西伊豆を潜るダイバー必携の図鑑だと思う。ただ、難点は、すぐボロボロになって、分解してしまうこと。 なお、本書は既に絶版であるが、たしか2004年に約80種ほど追加した改訂版\1890 (表紙がクマドリイザリウオ)が発行されている。 |
||||
 |
生態観察ガイド 伊豆の海水魚 | |||
|
瓜生知史 著 海遊社 \2800+tax 2003年1月10日 初版発行 2003年1月26日 購入 |
||||
| 約700種の魚図鑑であるが、この本の特長は、約44種について、その繁殖行動を複数の写真とともに 詳細な観察記録(観察ポイント)として、掲載されている点だ。ネコザメの産卵シーンや卵、 オハグロベラの噛みつきあい、キンチャクダイの放精シーンの写真など、興味深い生態写真が数多く載っている。 但し、少し残念なのは、ビデオから落とした写真があるため、きれいでない写真も含まれていること。 生態観察、その一瞬の撮影は難しいので、仕方のない部分もあるが、今の高解像度、高性能のビデオなら、 もう少しきれいな絵になったであろう、と思ってしまった。 しかし、ここまで生態活動を収めた図鑑はほかにないと思う。 | ||||
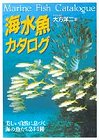 |
海水魚カタログ 美しい自然に息づく海の魚たち244種 | |||
|
大方洋二 著 永岡書店 \1553+tax 1997年8月10日 発行 1998年8月?日 購入 |
||||
| ダイビング始めてすぐに購入した数冊のうちの一冊である。当時、知っている魚といえば、 堤防・磯釣りの魚や食卓にのぼる魚ばかりであった。今(2005/5/12)、パラパラっと見直してみたが、 結構面白い。掲載種類は、副題のように244種と少な目ではあるが、 ダイバーの目につき易い身近な魚が多く、さらに、たっぷりの解説が、興味をそそる。 オニイトマキエイ(マンタ)のところでは、見開き2ページのところに、 解説に1/2ページ(文字数にして、約640文字)も割いてあり、頭鰭の形状、ホバリング、交接器、 出産方法(水面から2m空中にジャンプ?)など、たくさんのことを紹介している。 難しいことばかりでなく、実際の観察結果からの解説が多く、ためになる本である。 | ||||
 |
魚の不思議ウォッチング | |||
|
大方洋二 著 緑書房 \2667+tax 1997年10月20日 第1刷発行 1998年8月?日 購入 |
||||
|
観賞魚専門誌「フィッシュマガジン」に1989年から8年間連載された「大方洋二の海の生態学」
を加筆訂正して、まとめたものらしい。写真と文章、それぞれ、1ページずつで、構成されている。 1種類につき、1ページもの解説があることからも想像できると思うが、かなり詳しいことが書いてある。 写真の数も多いので、わかり易い。例えば、スミレナガハナダイのページでは、雄の写真、雌の写真、 その中間色の個体の写真があり、本文の中でも、この中間色の個体の行動についての記述がされている。 なかなか、面白い。掲載魚種が、明るくカラフルなものが多いのは、観賞魚専門誌に連載されていたからだろう。 |
||||
 |
山溪フィールドブックス6 海水魚 | |||
|
益田一 著 山と溪谷社 \2330+tax 1997年10月10日 初版第12刷発行 1998年7月?日 購入 |
||||
| ダイビングを始めて、最初に購入した魚図鑑である。1992年に初版第1刷が 発行されて以来の定番の携帯図鑑だと思う。 収録魚種は、1287種類もあり、小さな大図鑑と呼ばれている。 内容は、写真と和名と解説文1行程度(全長、撮影場所、撮影者、分布、生息場所) というシンプルな構成であり、収録魚種の多さの割りに携帯性に優れている。 ダイビングに持って行き、ログ付け時に見た魚の名前を調べるのに、都合がいいと思う。 | ||||
 |
山溪フィールドブックス8 海辺の生きもの | |||
|
奥谷喬司 編著 楚山勇 写真 山と溪谷社 \2621+tax 1997年12月1日 2版第3刷発行 1998年12月?日 購入 |
||||
|
この本も、小さな大図鑑と呼ばれ、1132種もの生き物が収録されている。
海綿類から始まって、ウミトサカ・ヤギ・ウミカラマツ類、イソギンチャク類、
クラゲ・サルパ類、ゴカイ類、巻貝類、ウミウシ類、二枚貝類、イカ・タコ類、
シャコ・エビ類、ヤドカリ・カニ類、フジツボ・ワレカラ類、ウミユリ・クモヒトデ類、
ヒトデ類、ウニ類、ナマコ類、ホヤ・マメクジウオ類、海藻・海草類まで、何でもござれである。 この本は、1994年に初版発行されているが、古さを感じさせない図鑑である。 それぞれの専門のガイドブックが発行されている生き物もいるが、 ダイビングに持っていくのに、この本はちょうどいい。 |
||||
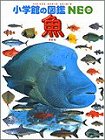 |
小学館の図鑑NEO 魚 | |||
|
井田齊・松浦啓一 監修・執筆 藍澤正宏・岩見哲夫・近江卓・萩原清司・成澤哲夫 指導・執筆 小学館 \2000+tax 2003年12月1日 初版第3刷発行 2004年4月19日 購入 |
||||
|
総合的学習に最適!!自由研究のヒントがいっぱい!!食べる魚や
見て楽しい魚など1100種の解説(オビ紹介より) この図鑑は、パラオのDSのガイドさんの紹介で知った。 その方も写真を提供しているとのこと。また、表紙の巨大なナポレオンは、 パラオで撮影されたものであるらしい。 このガイドさん、実は、某大学の水産学部?の院生であり、 その研究室の教授が、本図鑑の執筆者の一人という事であった。 この図鑑は、お子様向けである。但し、侮ってはいけない。 びっくりするほど中身が濃い。すごく判り易い上に、見やすい。 魚の観察の仕方や飼い方や、進化と仲間わけ、体のしくみまで掲載されている。 面白かったのは、魚の食べ物図鑑のコーナーである。魚の餌ではなく、人間が食べる魚のことである。 サケやブリなどの切り身が20種類、 アジやホッケなどの干物が21種類、 加工品として明太子やキャビア、マグロの水煮缶詰やちくわやソーセージまで、 写真付の解説が載っている。なかなかためになる本である。 |
||||
| 頁のTOPへ | ||||
写 真 集
5冊
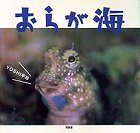 |
おらが海 | |||
|
YOSHI平田(平田吉克) 著 海游社 \2000+tax 1998年12月10日 初版発行 1999年?月?日 購入 |
||||
|
マレーシア・サバ州・マブール島のシパダンウォーターヴィレッジ所属(1999年当時)の
YOSHIさんのかわいい海の友達を撮影した写真集である。この写真集は、自分が、
仕事の都合がつかずに行くことができなかったマブールツアーに行って来た友人が、
お土産として買ってきてくれた・・・、のではなく、「すごくいいよ。」と紹介してくれたものである。 すごく表情豊かな小さな生き物たちが、それぞれ、簡単なコメントとともに、楽しげに出演している。 ユーモラスで、かわいく、明るく楽しい一冊である。 |
||||
 |
 |
Smile 〜 My Friends of Sea 〜 井上慎也写真集 | ||
|
井上慎也 著 東方出版 \1800+tax 2001年6月5日 初版第2刷発行 2003年7月18日 購入 |
||||
|
やさしい気持ちになれる本。難聴の写真家が、心の耳で聞いた「海の声」。
ページをめくれば、きっとあなたにも伝わります。(オビ紹介より) 全体的に明るいイメージの写真集である。海の生きものと親近感を感じさせるものであったり、 生態を教えてくれるものであったり、また、自然の中での迫力、躍動感を感じさせるものであったり、 海そのものの人を癒し、安らぎを感じさせる写真であったり・・・。 |
||||
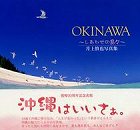 |
OKINAWA 〜 しあわせの島々 〜 井上慎也写真集 | |||
|
井上慎也 著 東方出版 \1200+tax 2002年9月10日 初版第3刷発行 2004年10月21日 購入 |
||||
|
沖縄はいいさぁ。18歳で沖縄に移り住み、「人生が変わった」という著者がとらえた沖縄の魅力たっぷりの写真集。
ゆったり流れる時間に身をまかせ、魚も鳥も花も、みんなごきげん!!(オビ紹介より) 沖縄の魅力って、なんだろう?もちろん、きれいな海をはじめとする魚や鳥や花もそうなんだろうけど、 それだけじゃなく、都会の人達が失ってしまった何かが、まだ、残っているからではないだろうか? 人として、人間として・・・、大事な何かを・・・。 |
||||
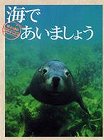 |
海であいましょう | |||
|
井上慎也 著 東方出版 \1000+tax 2003年7月30日 初版第1刷発行 2003年9月11日 購入 |
||||
| すっごくかわいいんですよ。ラッコやアザラシ、イルカやクジラもペンギンも。 そして、マンタやジンベイ、ピグミーシーホースまで。 そんな彼らの生態を楽しくわかりやすく語ってくれている。 そんな文章の中に、「そうそう、そうなんだよ!」と自分と同じ気持ちを感じて、 うれしくなったり、「へぇー、知らなかった。そうだったんだ。」と感心してみたり。とにかくかわいくて、面白い。 自分も、会ってみたいなぁと思わせられる写真集である。 | ||||
 |
in BLUE | |||
|
西田茂 著 光村推古書院 \1200+tax 1998年6月1日 初版第1刷発行 1998年11月19日 受贈 |
||||
| 題名のとおり、青い世界の中の作品が中心である。すがすがしい、切れのある感じの写真が多い。 ワイド系の写真が多く、微妙なライティングが・・・。う〜ん、こまったなぁ。 自分もワイド系の写真を撮りたくなってきたなぁ。 | ||||
| 頁のTOPへ | ||||
ス キ ル ・ 安 全
11種
 |
 |
だいこんダイバー!? Cカード取得後の必読書 | ||
|
赤木正和・田中光嘉 著 つり人社 \1400+tax 2008年7月15日初版 発行 2008年12月31日 購入 |
||||
|
久しぶりに、ダイビング関係の本を購入した。
帯紹介の「知らず知らずのうちにとてもキケンなこと、していませんか?」に惹かれたこともあるが、
最新の情報に触れてみたいという欲求もあったからだ。
実は、最近、周りのダイビングスタイルが、気になっていた。
リゾートなどの現地で、同じグループになった人達で、
安全停止の最中に、7〜8mに写真を撮りに行ったり上がったり、
浮上速度が異常に速かったり…、特に、安全停止終了後の5mを10秒ぐらいで、浮上しちゃう人とか…。
また、最近のダイビングコンピュータには、減圧停止指示だけでなく、安全停止指示がでるとか、
ディープストップとかの情報収集もしていましたが、
最近、ダイビング雑誌、ダイビングショップから遠ざかっていたので…。 で、内容は、正直あまり新鮮味はなかった。…というか、自分が普段、人に感じていることと ほとんどが、重なっていた。でも、自分も「友達なら言うのに…。」とか、 「友達でも、言いにくいなぁ。心配しすぎだよと言い返されちゃうかなぁ。」ということが、 しっかりと書いてあって、うれしい内容ではあった。「ホラ、これにも書いてあるよ。」と言えるから…。 まあ、そういう自分も、わかっているのに、「まぁ、いいか!」となってしまうこともあるし、 過去(将来も?)には、減圧症(幸い、完治済)に罹患し、 チャンバーに入ったことや、ついつい大深度に行ってしまったこともあるので、反省を促す意味でもいい本である。 そういえば、OWの講習時に、「ヨーヨーダイブが、よくないこと」を習った時、 講師(イントラ見習)に 「なぜ、よくないのか?浮上速度に気をつければ、最大深度の滞底時間が短くなるので、体内窒素は、少なくなるのでは?」 と質問し、明確な回答をもらえなかったことを思い出した。 「難しいことはわかりませんが、してはいけないことです。」で、済んでしまった。その後、自分で、調べたが、 この本は、簡単に解り易く説明してあった。ヨーヨーダイブは、炭酸飲料を振ったときに似ていると…。 もちろん、程度問題であり、ヨーヨーダイブの定義も不明確だし…。 水深◇◇mで上下振り幅○○mを△△回以上行うのがヨーヨーダイブであるとか、決めるのはナンセンスであるから。 最後に、今は、インターネットで、簡単に情報入手できるが、古い間違った情報も含まれているということを 認識するべきである。自分も本HPで情報発信しているが、特に減圧症(の治療)に関する情報は、日進月歩であるので、 最新の情報を確認することを忘れないようにしたい。 とにかく、副題のとおり、Cカード取得後の必読書という感じの本です。 |
||||
 |
からだとダイビング Q&A | |||
|
山見信夫 著 サンデイテイ \1600+tax 2002年3月1日 発行 2002年3月6日 購入 |
||||
|
この本は、月間ダイバー誌及びその別冊誌に掲載された記事に一部加筆修正されたものである。
若くて元気な頃は、そんなに気にしていないかもしれないが、年齢とともに、
身体のいろいろなところにガタがくる。そんな人は、必読な書である。 特に自分は、「肥満」とか、「高血圧」とか、 気になっている。そんな身体とダイビングの関係に対して、 丁寧に説明してある。また、「めまい」、「しびれ」、「頭痛」について、あくまで目安ではあるが、 フローチャートである程度の原因がわかるようになっている。 さらに、耳のスクイズから減圧症まで、様々な潜水障害についての原因・症状・対処法・予防法や 潜水障害と潜水事故のデータも多数掲載されており、たいへん参考になる。 |
||||
 |
危機からの脱出 55話 | |||
|
月刊ダイバー編集部・田辺慎一 著 渡井久美 編 サンエイテイ \1600+tax 2001年4月1日 発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
この本は、月間ダイバー誌に掲載された記事に一部加筆修正されたものである。
危機から脱出した話を聞いて、自分も同じような危機に陥ったとき、この本のおかげで、
同じように脱出できる・・・というものではない。なぜこの様な危機に陥ったのかを考え、
このような危機に陥らないためにはどうすればいいのかを考えるための本である。
予防のために、本書を読むのである。 自動車運転教習所で習う「かもしれない」運転と同じである。 あらかじめ、予防措置を講じておくのである。 しかし、それでも危機に瀕した場合は、 本書のような事例を参考にして生き抜いてほしい。 |
||||
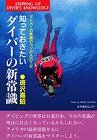 |
知っておきたいダイバーの新常識 | |||
|
唐沢嘉昭 著 水中造形センター \1400+tax 2001年4月15日 初版発行 2001年8月25日 購入 |
||||
|
ダイビングの世界は日進月歩。今日の常識が明日には古くなっているかもしれない。
アメリカの最新情報を元にダイバーの新常識をマスターしよう。(帯モドキ紹介より) 漫然とダイビングしていると気付かないこと、本来知っているべきだが知らなくても済んでいってしまっていること、 そんなことがたくさんある。ちょっと、知っているだけで、安全度が上がったり、より楽しめたり・・・。 一例を挙げると、タンク。世の中には、工事現場のアセチレンボンベ、病院の酸素ボンベ、家庭用のプロパンガスの タンクなどたくさんあるが、実は、ダイビングのタンクほど、 過酷な使用方法のタンクはないらしい。 充填圧力が非常に高く、短時間の間に使い切る。腐食性の高い海水中で使われる上に、 浮力とのバランスが必要なため、軽めにできている(タンク内壁の肉厚が薄い)。 キズなどから、腐食が進むこともある。だから、タンクの扱いは、「やさしく丁寧にね。」ということだ。 管理されているレンタルタンクと言えど、自分で外観チェックするぐらいは、したいものである。 |
||||
 |
ダイビング上達クリニック もっと上手になるために | |||
|
豊田直之 著 マリン企画 \1456+tax 1997年8月31日 第4版発行 1998年?月?日 購入 |
||||
|
基本的には、オープンウォーターのCカード取得時のテキストに書かれている内容であるが、
テキストより、より実践に合わせた内容といえる。悪い例や良い例を提示したり、
より細かい注意点や諸問題に対する対処法などが詳細に載っている。 例えば、フィンワークの仕方だとか、コンパスを使った行って来いナビゲーションだとか、 をこれでもかというぐらい細かく丁寧に解説してある。また、実際のボートダイビングの際、 着岸・離岸時に船べりに手をついている人をたまに見かけるが、 こういう点も注意点としてきちんと書いてある。 初版は、1994年発行であるが、内容は、10年以上たった今でも、十分通用する。 自分は、Cカードを取得して、すぐに本書を入手したが、それ以来、今でもたいへん参考になっている。 現在は、表紙の絵がよりポップになった新装版(2004/5〜)が出ているらしい。 |
||||
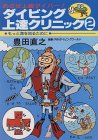 |
ダイビング上達クリニック2 もっと海を知るために | |||
|
豊田直之 著 マリン企画 \1650+tax 1996年4月20日 第1刷発行 1999年?月?日 購入 |
||||
|
この第2弾のテーマは、もっと海を知ろうということである。テーマどおり、前半は、海流や潮流、潮汐などの
海の様々な現象そのものと、風や前線、台風や天気図の読み方などの海洋気象学について、わかりやすく、
説明してあり、たいへん参考になる。ショップのツアーを使わず、個人でダイビング計画を立て、
バディーと潜る人には、必要な知識である。 後半は、足がつったとか水中拘束とかのセルフレスキュー、事故者発見時の対応や曳航、CPR などの本格レスキュー、及び、ロープワークと有害生物である。 セルフレスキューは、第1弾とテーマが重複している部分(例:ロープが絡まった場合)があり、 読み比べてみると面白い。本書では、対処法と予防法など、より判りやすく説明されている? |
||||
 |
新潜水士テキスト 送気調節業務特別教育用テキスト | |||
|
労働省安全衛生部労働衛生課 編 中央労働災害防止協会 \1748+tax 1998年7月15日 第1版第5刷発行 2000年2月18日 購入 |
||||
| 本書は、ダイビングを始めて1年半、ダイブマスターをめざそうとしていた時、購入したものである。 ダイブマスターの必須条件ではなかったので、潜水士の免許を取得したのは、 ダイブマスター認定後しばらくしてからの、2004年である。 このときに、本書が役に立ったかというと、それは、???である。 一度は、全頁に目を通してあるが、細かいところまでは、覚え切れるはずがない。 試験に役立ったのは、あるHPの試験対策用の要約版であった。 このテキストの要点を箇条書きにしてあり、重要ポイントを朱書きにしたHPで、 A4に4ページづつ印刷して、8枚。それを2週間ほど覚えただけで、合格した。 しかし、実際の法規等は、本書があると便利だと思うが・・・。今は、改訂版が出ているらしい。 | ||||
 |
誰も教えてくれなかった ダイビング安全マニュアル |
|||
|
中田誠 著 太田出版 \1553+tax 1999年5月28日 第7版発行 1999年6月26日 購入 |
||||
|
スクーバダイビングで死なないために!!死にたくない初心者のために。
初心者の身になって初めて綴られたダイビングの必読書。(オビ紹介より) 本書は、そのタイトルから、安全に潜るためのスキルアップの類の本だと思って、購入した。 しかしながら、その内容は、かなりショッキングなものであった。 ハワイでのファンダイビング時に、いい加減なガイディング(インストラクター)により、 事故に遭い、入院。その後のいい加減なショップとのトラブルについて、語られている。 ある意味業界を敵に回すような内容である。 全部を信じられるものではないが、結構考えさせられたりする内容である。 本書に出てくるようなインストラクターやショップも存在するだろうが、 素晴らしいインストラクターや、ショップも多数存在する。結局は、それらを選ぶのは、 自分自身ということになるので、「初心者の皆さんは、気を付けて下さい。」ということである。 |
||||
 |
事故に遭いたくない人のための ダイビング生き残りハンドブック |
|||
|
中田誠 著 太田出版 \1550+tax 1999年5月28日 発行 1999年6月26日 購入 |
||||
|
内容は、事故の実態など、かなり過激であるし、表現方法が若干きびしめである。
いい加減な業界(一部だと思うが・・・)に対しての怒りが抑えきれない感じがする。
しかし、過去の事故や事例などは、ダイバーなら知っておくべきことであると思うし、
ダイバー仲間で本書の内容を話し合ってみるといいかも。 良いダイビングショップの選び方や、役に立つ話などは、参考になる。 |
||||
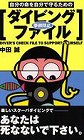 |
自分の命を自分で守るための ダイビング事故防止ファイル |
|||
|
中田誠 著 太田出版 \1550+tax 2000年6月14日 初版発行 2000年00月00日 購入 |
||||
|
業界に対しての問題点を提起している。様々なデータと体験談で、事故防止に貢献しようともしている。 シリーズ全体を通して、自然の怖さではなく、人間の怖さの方に主眼が置かれていると思う。 第5章「泣き寝入りしないために」は、法的責任や良い弁護士の探し方など、もしものときに参考になる。 |
||||
 |
ダイバー漂流 極限の230キロ | |||
|
小出康太郎 著 新潮社 \486+tax 2000年10月10日 発行 2000年?月?日 購入 |
||||
|
太平洋のまっただなか、男は、首ひとつ出して流されていった!
救命ボート、食料があってすら、遭難者は漂流3日以内に絶望し自殺するという。身一つで流された
ダイバーが、新島から銚子沖までの230キロを生き延びた!!(カバーの紹介文より) これは、すごいドキュメントである。もしも、自分だったらと考えると、恐ろしくなる。 すごい精神力である。自分は、初沖縄(経験本数7,8本目ぐらい)の時、 数分間の漂流を経験した。 この時は、経験がない(無知すぎる)ことが幸いして、恐怖感を味わうことなく、十数分で救助された。 今、考えると恐ろしい。この本で、どのようにして、冷静さを保ち続けたのか、 生きる気力を失わないようにしたのかを知って欲しい。 |
||||
 |
ダイバーズバイブル pert1〜5 | |||
|
小出康太郎 著 アクアプラン pert1,4,5 \2330+tax pert3 \2136+tax pert1 1997年12月 初版第5刷発行 1998年or1999年 購入 pert2 1994年12月 初版第3刷発行 2006年5月21日 購入 pert3 1994年5月満潮時 初版第1刷発行 1998年or1999年 購入 pert4 1994年10月満潮時 初版第1刷発行 1998年or1999年 購入 pert5 1995年6月満潮時 初版第1刷発行 1998年9月18日 購入 |
||||
|
ダイバーズバイブルは海の道先案内人。海を知り、潜水技術を高めることで、危険を回避し、
ひいては楽しいダイビングを行うための虎の巻です。 パート1は潜水事故の防止と回避を目的に多くの事例を取り上げ、 それらをケーススタディすることで疑似体験をする。海では万が一の局面に対処できるかどうかが 生死の岐れ道。本書は読むだけで潜水技術が向上、知らぬうちに海とのつきあいかたがわかり、 命を守ることにつながる。(オビ紹介より) パート3は「海と対峙し、海に迫る」、パート4は「海の優雅と魔性を探る」、 パート5は「海の神秘と不思議を探る」をテーマにプロ、アマが結集して、凄まじい話、奥義に触れる話、 心に響く話など、多岐にわたるケーススタディが満載。それぞれが、意図せざるノンフィクションとなって、 潜水と海のエキスを示唆します。(それぞれのオビ紹介より) まだ、初心者と言われる頃に、本書に出会い、ダイビングに対する怖さをより強く感じた。 当時、ショップのイントラに、「考えすぎずに、もっと楽しみましょう!」と言われたぐらい、 心に響き考えさせられた。 自分自身も、小学4年生の時、海水浴でおぼれた経験がある。 海をなめてはいけない。何が起こるかわからない。常に危機感を持ち、危機にならないように、予防策を講じておく。 さらに、それでも危機に陥ったときのために、その対策を頭の隅に入れておく。 本書の事例に対して、自分はこうはならないと思うのではなく、もしも自分だったらどうするか イメージトレーニングしておくことが大切だと思う。 ずっと、手に入らなかったpart2を入手しました。過去の事例はを参考にしないとね。 |
||||
| 頁のTOPへ | ||||
南 の 島
14冊
 |
ダイバーはパラオの海をめざす | |||
|
太田耕輔 著 集英社 \1500+tax 2000年2月21日 第1刷発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
あなたは海に溶けたことがありますか?第1章「海に出かけよう!」、第2章「ヘンタイでいこう!」、
第3章「ヘンタイ、海に挑む」(オビ紹介より) 自分は、パラオの海に初めてやってきたのは、タンク本数38本の時であった。 まだ、ダイビングを始めて、8ヶ月。ダイバー憧れの海といわれているこのパラオに、 こんなに早くやってきていいものだろうか。やはり、経験不足であった。 パラオの表面的なところだけを体験していっただけだったような気がする。 その後、400本近くなってパラオを再訪した時には、ヘンタイダイバーになっていた。 あのブルーコーナーで、大物は見ずにアケボノハゼとヘルフリッチの撮影に夢中になり・・・、 9本中7本をコロールから10分ほどの内湾で砂泥地のハゼ撮影に没頭したり・・・、 桟橋前の水深1.5mのところで 100分超の間オイランハゼのホバリングを狙ったり・・・。 最近、読み直したら、「そうそう!」、「そのとおり!」と同意できる部分がすごくたくさんあった。 また、ただ面白おかしく楽しいだけでなく、環境問題に対してのそれぞれ立場の違う人の問題等、 興味深い内容もある。パラオ経験本数45本(2005年5月)であるが、まだまだ、パラオの海をめざしたい。 |
||||
 |
沖縄で暮らす!! | |||
|
太田息吹 著 同時代社 \1500+tax 2000年5月28日 増補改訂版第1刷発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
豊かな自然、ゆったりとした時の流れ、あたたかい人情・・・・・・
私たち、沖縄に移住しました。著者自身の体験から得た、ガイドブックにない沖縄での
「暮らしの情報」を知る、実用ノンフィクション。
【沖縄移住人16名のインタビューを収録!!】(オビ紹介より) 沖縄に移住したいと考える人は、結構いるらしい。旅行で行ってみて良かったから という単純な理由で移住して、こんなはずでは・・・と思う人もいる。 行く前に沖縄の色々な情報を入手するのに、役立つ本である。 メリット、デメリットの両方をしっかり理解するには、いい本だと思う。 どちらかと言えば、デメリットは少なめのような気もするが・・・。 |
||||
 |
「最後の楽園」サモアで暮らす | |||
|
鳩山幹雄 著 風媒社 \1600+tax 2000年9月20日 第1刷発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
海がある、風がある、光がある・・・一家六人の楽園移住物語。
『パパラギ』の島・サモアに家族まるごと移り住む!
「シンプル・イズ・ベスト」な南の島の智慧に学ぶ。(オビ紹介より) 南の島での生活に憧れている人は、ぜひ読んでみて欲しい。ますます、行きたくなるか、 自分には無理だと思うか、それは、その人しだいである。このドキュメントの中では、 特に3人の子ども達の存在が光っている。 |
||||
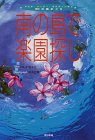 |
南の島で楽園探し | |||
|
いしいきよこ 文 石井正孝 写真 東京書籍 \1800+tax 2000年8月4日 第1版発行 2001年7月14日 購入 |
||||
|
タヒチ、フィジー、ニューカレドニア、サモア、トンガ、モルディブ、
サイパン、パラオ、ハワイなど30島を南の島の達人が「ホンネ」で紹介。
目的があるたびは面白い。けれどヤシの木陰に寝転がって何もせず、ただ、青い海を眺める。
これほど気持ちよい過ごし方を、私はほかに知らない。さあ、そろそろ、そんなたびに出かけよう。
すべての旅人のこころをほどく、南の島へ行こう!(オビ紹介より) この本は、きれいな写真が多く、南の島へ行きたい願望を増大させる。 明るく楽しげな南の島の青い空、白い雲、青い海、白い砂浜、カラフルなフルーツ、 元気一杯の現地の子ども達。これらの写真と紹介文に心がワクワクさせられる。 |
||||
 |
いつかは住みたい南の島 | |||
|
いしいきよこ 著 ミスター・パートナー \1300+tax 2000年12月20日 初版第2刷発行 2001年7月14日 購入 |
||||
|
あなたの夢もきっとかなう!仕事、留学、結婚・・・、太平洋の彼方で自分の人生を行きたい。
島に住む12通りの日本人の夢と現実を描いた待望のノンフィクション。(オビ紹介もどきより) それぞれの島に移住?して根を張った日本人に、著者が訪問・取材したことを 会話形式を交えながら、紹介してくれている。生の声が聞ける。移住じゃなくても、一度は行ってみたいと 思わせられる島がたくさん紹介してある。 |
||||
 |
1日1000円で遊べる南の島 | |||
|
林和代 著 双葉社 \1600+tax 2003年7月10日 第1刷発行 2004年4月19日 購入 |
||||
|
島好きライターが歩いて集めた最高の島世界28島トラベルガイド。
島旅&シュノーケリング講座付き(オビ紹介より) 「この人すごい」というのが、正直な感想であった。とにかく、一人(たぶん)でどこにでも行く。 1日1000円と言ってはいるが、ホームステイとかも利用している。今までの人脈の賜物である。 この人脈は、一朝一夕には作れないとは思うが、同じようなことができる人もいるかもしれない。 人脈を形成するための費用も入れると、1000円は無理のような気もするが・・・。 自分にとって、現実離れしているので、読んでて癒された。ただ、まだ、全章読破していない。 それぞれの島をそれぞれ楽しむために。 |
||||
 |
パラオ海中ガイドブック | |||
|
佐藤良一 著 阪急コミュニケーションズ社 \2400+tax 2003年7月29日 初版発行 2003年11月30日 購入 |
||||
|
パラオ、そこは神の宿る海。心も体も海に染まる。エントリーした瞬間に始まる至福のひととき。
パラオがあなたを待っている。(オビ紹介より) この本の著者は、別に紹介している「ダイバーはパラオの海をめざす 太田耕輔著」の中に 出てくる佐藤さんではないか。この時の掲載写真はサトウさんが撮影したと書いてあった。 もしかしてと思い、本書と比べてみると、2枚の共通の写真を発見した。 ネジリンボウの正面UPとアケボノハゼのUPだ。自分が撮影してみたい写真だ。 そういえば、初めてパラオに行ったとき、PPRの中のスプラッシュだったか、フォトパラオの中に、 大きく伸ばしたアケボノハゼとヘルフリッチの写真があった。特に、ヘルの写真は、印象に残り、 こんな写真が撮りたいと思ったような気がする。 きっと、佐藤さんは、太田さんに写真の使用のお願いをされた時・・・、 太:「このヘルフリッチの写真、使ってもいい?」 佐:「ヘルフリッチは、ダメです。」 (いつか自分の写真集を出すから・・・。) 太:「どうしても?」 佐:「どうしても!」 太:「じゃあ、アケボノハゼ使わせてよ!?」 というやり取りがあったのでは?と勝手に想像して楽しんでしまった。 (ごめんなさい。太田さんも佐藤さんも面識ありません。) 本書に載っているヘルフリッチの写真は、まるまる1ページを使っている。 本当に自信作なんだと思う。 ところで、本書は、写真集ではない。しかし、ガイドブックとしての利用とともに、 図鑑、写真集としての楽しみもある。パラオに行くなら、ぜひ一冊。 |
||||
 |
楽園パラオ2005 | |||
|
舘石昭 編集 水中造形センター \1219+tax 2004年12月1日 発行 2004年11月26日 購入 |
||||
|
海と島の旅の増刊号である。パラオの水中、各ダイビングスポット、滞在スタイル、
陸上でのお店紹介、出入国カードの書き方からアクセス方法、パラオにダイビング旅行するのに
必要なこと、すべてが載っているといってもいい。 雑誌の別冊なので、元雑誌のパラオに関する特集記事、及び、その時載せられなかった 取材内容に最新情報を追加して再編集されたものと考えてよい。 しかし、たくさんの情報が掲載されており、役に立った。 だからといって、2006年版を買うかというと、たぶん買わないとは思う。 今度は、2010年版ぐらいなら買うかも。 |
||||
 |
楽園の旅2004 | |||
|
舘石昭 編集 水中造形センター \1886+tax 2003年12月1日 発行 2003年11月?日 購入 |
||||
|
水中造形センターのダイビング関係4誌「海と島の旅」、「マリンダイビング」、
「マリンフォト」、「ダイビングスクール」による共同編集。
世界126エリアのダイビング&ビーチリゾートの最新情報が満載。 パスポート&ビザの取り方や出入国カードの書き方、海外ダイビングの基礎知識、 トラブル対処法、輸入感染症の予防対策、両替テクニックとチップマナーなど、 必要な情報を収録してある。写真も多く、各ダイビングリゾートの写真を眺めるだけでも癒される? |
||||
 |
ダイビング旅行完全ガイド 地球の潜り方 | |||
|
地球の歩き方編集室 編著 ダイヤモンド・ビッグ社 \1640+tax 2000年7月28日 初版発行 2000年?月?日 購入 |
||||
|
世界中のダイビングエリアについて、エリアの概要、トラベルガイド、ダイビングガイド、シーズナリティ、
ダイビングポイント、ダイビングスタイル&パターン、申込み方法、ダイビングサービス、レストラン、
ホテル、旅の予備知識(ルート、旅づくり、インフォメーション)について、詳細に収録されている。 既に、購入から5年余りが経ち、若干情報が古くなっている。最新版も出ているらしい。 |
||||
 |
沖縄・離島情報 平成13年夏号 | |||
|
林檎プロモーション \457+tax 2001年6月18日 初版発行 2000年?月?日 購入 |
||||
| この本は、すごくコストパフォーマンスの高い情報誌です。500円を切る値段で、情報満載です。 バスや連絡線の時刻表から、見所、食べ所、買い所、遊び所、泊り所などなどまで、 簡潔で詳細な紹介をしてあります。自分の利用したことがある店も何軒か載っている。 次回、17年夏版は購入したい。 | ||||
 |
 |
沖縄・離島情報 2006年度版 | ||
|
林檎プロモーション \743+tax 2005年12月8日 初版発行 2006年3月2日 購入 |
||||
| 以前に紹介した、沖縄・離島情報平成13年度夏号が、非常に魅力ある雑誌だったので、 最新版が欲しいなぁと機会がある度に探していたら、ついに見つけられました。 国際通りのとあるお店。「あれぇ〜、ちょっと大きくなってるなぁ。あっ、値段も高くなっている。」と 思いながら、購入。コレは、年度版だったのですね。 この本とは、別に、安く小さな春号、夏号が毎年出ているみたいです。 もちろん、この本も、バスや連絡線の時刻表から、見所、食べ所、買い所、遊び所、泊り所などなどまで、 簡潔で詳細な紹介をしてあります。春・夏号よりも若干情報量が多いかも? でも、持ち運びには、春・夏号のがいいかも。次回は、20年春号ぐらいを購入したい。 | ||||
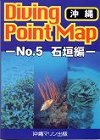 |
ダイビングポイントマップ −石垣編− | |||
|
沖縄マリン出版 \1900+tax 2000年10月25日 初版第1刷発行 2001年7月14日 購入 |
||||
| 購入目的は、自分が良く潜っていた石垣の海、そのポイントマップを見ることにあった。 石垣は、広範囲にたくさんのダイビングポイントが存在する。ダイビングサービスによって、 利用しているポイントも違えば、オリジナルポイントを利用しているショップもある。 残念なことに、自分が良く行くポイントは、あまり載っていなかった。 このような本は、よく中身を確認して購入した方が良い。 最近、よく利用するインターネット通販では、中身確認はちょっと難しい。 | ||||
 |
とにかく通じるダイバー英語 | |||
|
月刊マリンダイビング 編 水中造形センター \1359+tax 1998年10月20日 第7版発行 1999年?月?日 購入 |
||||
| ダイバーに必要な最低限の英語が載っている。まず、ダイビング器材の名称、ダイビングでの動作、そのあと、 場面別の英会話。空港・機内、入国審査、ホテル、タウン、ダイブツアー申込み、支払い、移動ボートでの情報収集、 ダイビング準備、バディとの会話、水中写真、アフターダイブ、天候・海況、海の生物、体調など。 なお、英語版生きもの図鑑もログ付け時に便利かも。 | ||||
| 頁のTOPへ | ||||
読 み も の
8冊
 |
動物奇想天外! 仲良しサカナ組 | |||
|
中村征夫・さかなクン(宮澤正之) 著 三五館 \1300+tax 2002年8月6日 初版発行 2002年?月?日 購入 |
||||
| 中村征夫さんとさかなクンの会話形式で成り立っている。二人の軽妙なやりとりで、 魚の特徴や生態が解説されている。その中で、70問あまりの問題が散りばめられており、 楽しく問題を解くことができる。 実は、あのさかなクンの甲高い声が苦手なのだが、当然、本書を読む上であの声を 聞かなくてすむと思っていたが、なぜか、さかなクンのあの甲高い声と征夫さんの 渋い声が聞こえてくるのであった。 | ||||
 |
ダイビングの世界 | |||
|
須賀潮美 著 岩波書店 \740+tax 1999年6月21日 第1刷発行 199?年?月?日 購入 |
||||
|
ふんわりゆらゆら海中散歩。初めて沖縄の海で潜ったときの感動は、今でも鮮明に覚えている。
・・・「ジャブン」と海に飛び込むと、20kg近いスクーバダイビング器材の重さから開放され、
フィンを動かすだけで羽がはえたように自由に浮遊できる。水面を見上げれば光のシャワーが降り注ぎ、
目の前にはブルーやオレンジ、黄色など色とりどりの魚たちが乱舞する。
海面下に広がる美しい風景に心を奪われた。(オビ紹介より) 著者が水中リポーターだとは知らなかったし、水中リポートも見たことがなかった。 本書を読んでから、一度だけ水中リポートを見たことがある。スターウォーズのダースベーダーのように、 「スゥーコォー(ゴボゴボ)、ズゥーゴォー(ゴボゴボ)」という呼吸音とともに、目の前の魚の説明をしていた。 著者は、日本全国、北から南、さらに世界各地の海に潜っている。 特に、印象に残ったのは、諫早湾の干拓堤防の件である。 最近(2005/5)、地裁の工事中止の仮処分の判決を高裁が逆転棄却の判決を出した。 諫早湾の干拓工事が始まった後に、名古屋のごみ処分場として 藤前干潟の埋立計画が急浮上してきたが、 中止になった。その後、名古屋市は、ごみ非常事態宣言をして、 ごみ減量に努めている。(効果もかなりある。) この時、環境アセスメントのやり方や干潟の重要性について、かなり議論されていた。 藤前干潟埋立て中止の経緯は、本書にも掲載されている。 とにかく、諫早湾の工事中止の仮処分の棄却は、残念である。 自分は当事者ではないし、工事の必要性の真偽を確かめられる立場にもないので、 「どちらかといえば、埋め立てて欲しくないなぁ。」ぐらいの立場にしておく。 そういえば、中村獅童と結婚することになった竹内結子主演ドラマ 「不機嫌なジーン」でも、この問題が出てきてたなぁ。 2005/05/20 |
||||
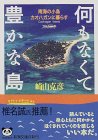 |
何もなくて豊かな島 南海の小島カオハガンに暮らす | |||
|
崎山克彦 著 新潮文庫 \476+tax 1998年11月1日 発行 199?年?月?日 購入 |
||||
|
会社を辞めて移り住んだ南の島には、新しい人生があった。美しい自然、ゆったり流れる時間・・・。
「豊かさ」とは何かを問いかける本。(新潮文庫最新刊紹介文より) すごいですねぇ。退職金で、住民350人の島民が暮らす島をまるごと買ってしまうなんて。 そして、その島民の暮らしを壊すことなく、島での生活を始めている。 現実に、自分もできるかどうかは別として、こんな生き方もあるんだなと・・・、 ちょっとうらやましく思ってしまう。 |
||||
 |
ドルフィン・ピープル | |||
|
小谷実可子 著 ●●近代文芸社 \1500+tax 1998年8月5日 第1刷発行 199?年?月?日 購入 |
||||
|
小さい頃からの夢だったオリンピック、最終ゴールだったはずの場所にたどりついた時、
思わぬ付録が付いてきた。“イルカに近い人間”小谷実可子、初のエッセイ集。(オビ紹介より) シンクロナイズドスイミングの選手はスキンダイビングをしても、きっと一流なんだろうな。 そして、優雅できれいに潜るんだろうな。そう、思いながら、本書を読んだ。 前半は、シンクロ時代の自伝で、一流スポーツ選手の苦労と努力と楽しさと喜びの物語である。 そして、後半はイルカと出会った、ある意味第2の人生の物語。おもしろいっちゃーおもしろい。 あまり周りのものも見ず、一直線に突き進んできた人が、なにか別の世界に出会い、目覚めていく。 そんな様子に自分も引き込まれてしまったかも・・・。 |
||||
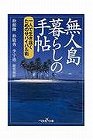 |
無人島暮らしの手帖 一人で生き抜くためのサバイバル術 | |||
|
朴相俊(パクサンジュン)・朴敬秀(パクキョンス)・李宇逸(イウイル) 著 羅愛蘭(ナエラン) 訳 新潮社 \619+tax 2001年11月10日 発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
目を覚ますと、そこは無人島の波打ち際。全財産は、カメラ、ナイフ、ライター、雨具、
眼鏡にビニール袋少々・・・。あなただったら、何日生き延びられます??(裏表紙カバー紹介文より) 著者が、韓国の方だとは知らずに本書を購入した。文化的背景などにより、若干違和感を感じる部分もあるが、 まあ、おもしろく読ませていただいた。この本を購入した理由は、当時、テレビでネプチューン司会の「サバイバー」 という番組を見ていた影響と表紙の写真が「南の島」っぽかったからである。内容的には、飛行機に乗っていた主人公が 一人で、無人島の海岸に打ち上げられているところから、始まる。なぜか、ウェストバッグを身につけており、 その中には、ナイフが入っている。 今のセキュリティの厳しい状態でナイフを身につけたまま飛行機に 乗ることは難しいと思う。 |
||||
 |
ウはウミウシのウ シュノーケル偏愛旅行記 | |||
|
宮田珠己 著 小学館 \1300+tax 2000年3月20日 第1版第1刷発行 200?年?月?日 購入 |
||||
|
本書の冒頭に「この本の収益の一部を、かけがえのない世界の海とそこに棲む生きものたちを、
私が見に行くために捧げたい。」とある。ふざけている。わざわざ、書かなくとも印税をどのように
使おうが知ったこっちゃない。著者は自慢したいのだ・・・、たぶん。
「印税入ったら、また、面白い変なカタチの海の生きものを見に行ってこよう!」てな具合である。 本書を読んでも、海の生きものの生態について理解は深まらないと明記されている。 著者がシュノーケルで見て回った変なカタチの生きものについて、報告されているだけである。でも、面白い。 旅行記なので、生きものだけでなく、旅先で出会った人との楽しい会話や面白い体験なども載っている。 とにかく、ふざけているが面白い。 |
||||
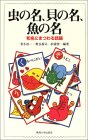 |
虫の名、貝の名、魚の名 和名にまつわる話題 | |||
|
青木淳一・奥谷喬司・松浦啓一 編著 東海大学出版会 \2800+tax 2003年2月5日 第1版第2刷発行 2003年3月12日 購入 |
||||
|
ダイバーでも、魚の名前を覚えるのが、得意な人と不得手な人とがいる。
魚の名前をたくさん知っていたところで、実生活でそんなに役に立つわけではないが、
ログ付けの時、名前をしていると楽しい。また、判らない魚を図鑑で調べたりするのもいい。
そんな時、一般的に使われているのが、和名である。 本書は、その和名についていろいろなことが語られている。 「ニセ」、「ダマシ」、「モドキ」が付く和名について語られていたり、 スズキ目ネズッポ科に属する魚は、なぜか「○○ネズッポ」とか「ネズッポ○○」はなく、 「○○ノドクサリ」と「○○テグリ」であるとか、知っていても役に立たない知識が多い。 また、どうしてそのような和名になったのか、わからないものも多い。 |
||||
 |
アクアリウム | |||
|
篠田節子 著 新潮社 \476+tax 1999年1月15日 8刷発行 1999年?月?日 購入 |
||||
|
長谷川正人遭難したダイビング仲間を探すため、奥多摩の地底湖に潜った。そこは水没した鍾乳洞で、中は迷路のようだった。
自分の位置を見失ってしまった正人は死を覚悟するが、突如現れた「彼女」に導かれ、奇跡的に生還した。
あれは幻覚だったのか?それとも・・・、正人は「彼女」の姿を求めて再び水底へと向かう。だが、そこで見たものは・・・。
新感覚のサスペンス・ファンタジー。(裏表紙カバー紹介文より) ダイビング関係の小説だと思って購入したが、思惑とはかなりずれていた。 不気味でホラーっぽい部分もあるし、 神秘的な部分もある。SFっぽくて、サスペンスでもある。 環境問題っぽいところもあったりする。気持ち悪い部分もあるが、引き込まれて読んでしまった。 |
||||
| 頁のTOPへ | ||||
漫 画
4種
 |
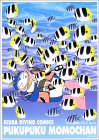 |
ぷくぷくモモちゃん | ||
|
桃伊いづみ 著 TBSブリタニカ \1200+tax 2002年9月28日 初版発行 2002年10月12日 購入 |
||||
| 月刊ダイバーに連載されているダイビングまんが。毎号ひとつのテーマを4コマ漫画3話形式で掲載されている。 とにかく、ほのぼのとさせられる。フィッシュウォッチングでの面白体験、エピソードが満載、「そうそう!」と 共感できることがうれしい。 | ||||
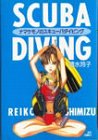 |
ナマケモノのスキューバダイビング | |||
|
清水玲子 著 白泉社 \800+tax 1998年4月30日 初版発行 1999年11月20日 購入 |
||||
|
スキューバダイビングをはじめたい人に贈る清水玲子のドキドキ体験まんが。
人魚になって、カラフルなお魚さんたちと泳ぎたい、という夢をかなえてくれるダイビング。
とはいえ、いろいろ心配もあるアナタへ、充実した記事ページも満載。
読んでいるだけで、ダイビング気分も味わえる、ナマケモノにぴったりの一冊です。
(裏表紙カバー紹介文より) 表紙を見て、「この人の絵、きれい!」と思ったが、実際の中身は、 ほとんどギャグマンガチックなタッチの絵であった。 内容もダイバーのほとんどが経験するような笑える話が多い。 プール講習の最中にトイレに行きたくなった話とか、海洋実習が10月の伊豆だったので、 寒くて途中リタイアした話とか、結局、わざわざマイドライスーツを作って、 さらに寒い11月の伊豆での再講習で合格した話とか・・・。 |
||||
 |
イオ 全10巻 | |||
|
恋緒みなと 著 講談社 \505〜552+tax 第1巻 2000年4月6日 第1刷発行 第10巻 2005年3月4日 第1刷発行 ヤングマガジン1999年第1号〜2004年第6号掲載 |
||||
|
沖縄座間味を舞台にしたダイビングSFファンタジー漫画である。・・・と思う。
ヤンマガを読んでないので、たまたま、本屋で単行本第1巻を見つけた時は、うれしかった。
もちろん、ビニール袋に入っているので、中身の確認はできなかった。
しかし、表紙は、女の子がボートの上で、すごくリアリティーのある器材のセッティングを
しているような絵だった。 東京の高校生、仲原太洋は、修学旅行で沖縄に・・・、そして自由行動の時間に 水中写真家だった父が10年前に行方不明になった座間味の海に向かうのだった。 そこで、渚、沫、澪という三姉妹に出会う。太洋は、昔、この姉妹達とこの島に住んでいたらしい。 泊港の「とまりん」の建物や連絡船「クイーン座間味」やダイビング器材が、妙にリアルに書き込みしてあり、 なんだかワクワクしてきたが、だんだん現実離れしてしまうのと、実際のダイビングでは無理な状況に ちょっぴり「?」と感じながらも、まあ、フィクションなので、しょうがないかなという感じである。 |
||||
 |
「RAKUEN」 大吉・凛々子のLOG BOOK | |||
|
今谷鉄柱 著 集英社 \505+tax 2001年1月24日 第1刷発行 200?年?月?日 購入 |
||||
| ダイビング漫画なんだけど、ダイビングのシーンは、あんまりない。 恋愛ものです。ちょっと環境問題も入っているかも・・・。 | ||||
| 頁のTOPへ | ||||
カ メ ラ
5冊
 |
 |
おさかな接近術 水中撮影ガイドブック | ||
|
白鳥岳朋 著 TBSブリタニカ \2600+tax 2001年7月26日 初版発行 2001年8月25日 購入 |
||||
|
さかなの生態がわかれば、写真はもっとうまくなる!
めざせ!マクロハンター!!プロが教えるワンランク上の水中撮影テクニック!(オビ紹介より) 本書は、ただ単に「撮影技術」という言葉で表すより、「被写体を見つける技術」、 「被写体の表情を引き出す技術」のようなもう一歩踏み込んだ技術が満載である。 体色&模様、食べる、お気に入りの場所、共生&クリーニング、群れ&ペア、擬態、交尾、産卵、抱卵などの テーマごとにまるで写真集のように写真が収録されている。それぞれの写真に絞り、シャッター速度などの 撮影データの他、撮影時の状況、心境なども添えられている。写真を見て、「こんな写真撮りたい。」と思えば、 似たような写真が撮れるかもしれない。ある程度、撮影技術のある人向きかも・・・。 いや、見てるだけでも楽しいかも・・・。 |
||||
 |
 |
水中写真 虎の巻 | ||
|
白鳥岳朋 著 マリン企画 \1941+tax 1996年6月22日 第2刷発行 199?年?月?日 購入 |
||||
| 水中写真の基本が満載。第1章「器材の買い方、選び方」では、ビューファインダーカメラと 一眼レフカメラの違いから始まって、レンズの基礎知識、ハウジング、ストロボ、及びセッティングまで。 第2章「撮影の基礎知識」では、フィルムに映像が写るわけから始まって、絞り、シャッター速度、露出、 ニュートラルグレー、レンズの特徴、ストロボまで。ストロボのガイドナンバーと絞りの関係など、 結構難しい内容もわかりやすく説明してある。陸上でも重要な焦点距離・画角・遠近感についてや、 絞りと被写界深度の話など、写真撮影の基本・基礎は、たいへんわかり易い。 第3章「撮影の極意」では、自然光撮影、ストロボ撮影、ミックス光撮影、ライティング、超広角&広角、 マクロ撮影などのそれぞれのポイントが、明確にわかりやすく紹介してある。 第4章「写真は、フィーリングだっ!」では、構図や図鑑的撮影法、魚の見つけ方、近づき方などのハードではない、 ソフト面の紹介がしてある。たいへんためになった。陸上写真をされていた方は、 撮影の基礎知識の半分は不要であると思われるが、ストロボなどの水中撮影独特の使用方法は、参考になる。 | ||||
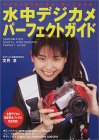 |
水中デジカメ パーフェクトガイド | |||
|
文月凉 著 マリン企画 \1500+tax 2001年5月20日 第1刷発行 2001年?月?日 購入 |
||||
|
もともと、ダイビング始めたときに、35万画素のデジカメを持っており、それを水中に持って行きたくて、
行きつけのショップのイントラに相談したが、あっさり却下され、一眼レフ&ハウジングを始めた。 しかし、オリンパスのおかげで、水中デジカメは爆発的なヒットをし、水中写真の世界が より入門しやすく手軽になっていった。既に銀塩水中写真にどっぷりはまっていた自分は、サブカメラとして、 オリンパスのデジタルカメラC−1を購入した。その時に、デジカメとしての専門書として、本書を購入。 実は、著者のホームページが立ち上がった頃、偶然、立ち寄らせてもらい、当時、 オリンパスのハウジングの出る前に、QVシリーズ(メーカー忘れた)で、専用のハウジングを作って、 レポートしていたのを覚えている。その著者の執筆した本であるので、思わず購入してしまった。 最新の著書「Digital Diver 水中一眼レフデジカメ徹底リファレンシャルガイド」も、購入したい。 |
||||
 |
デジタルカメラでかんたん水中写真 | |||
|
清水淳 著 サンエイテイ \1200+tax 2001年6月1日 発行 2000年99月99日 購入 |
||||
|
2001年GW前、デジタルカメラ「オリンパスC−1」を購入した。
もともとでっかいハウジングは、持って潜っていたので、サブカメラとして、コンパクトなデジカメが
欲しかった。画素数は、当時としても少なめの130万画素。ズームもない。
しかし、BCのポケットに入るし、電池寿命も長めだったので、証拠写真撮り、スナップ撮りに最適だった。 そのカメラの入門書として、本書を購入した。当時のオリンパスの最新機種C-1(PT-008)、 C-3040(2040)ZOOM(PT-007)、C-460ZOOM(PT-006)の三機種に特化した入門書であった。 ただ、C-1の出番は、あまり多くなかった。内容は、ほんとに入門書であり、初心者にはいいと思う。 |
||||
 |
AF一眼レフ入門 | |||
|
丹野清志 著 ナツメ社 \1000+tax 1995年2月20日 初版発行 1995年?月?日 購入 |
||||
|
今回、ご紹介している本の中で、唯一、ダイビングを始める前に購入した本である。
1995年に初めて買った一眼レフカメラが、ミノルタα303siSUPERであった。
キャノンEOS-KISS(初代)のライバルとして登場したが、あまり、ぱっとしなかったようだ。
「SUPER」という名称は、前号機のマイナーチェンジで追加されたもので、
レンズマウントがプラスティックからメタルに変更になって、信頼性が向上した。
とにかく軽いく扱いやすく気に入っていたが、EOS-KISSを買っていれば、
ダイビングを始めた時に、ニコンF90に買い換えなくては済んだのではと、ちょっと残念に思っている。 この本は、そんなまったくの一眼レフ初心者だった自分のテキストともいえる本である。 ただし、カメラ・レンズの基礎的なことについては、あまり、詳しくは書いてない。 この本の中で、一番印象に残ったのは、次の文章である。 「『どうにもうまく写らないんですよ。』とグチる人がいる。たいていそういう人は、 写真を好きで写しているのではなくて、何かがあって、たまにカメラに触れる人。 写真が好きで写している人は、自分でなんとか工夫しているから、どうしたらうまく写るか、 などと不平をもらさない。工夫することが写真の楽しさだということを理解しているからだ。」 ・・・そう、工夫なんですよね。 |
||||
| 頁のTOPへ | ||||
TOP頁に戻る